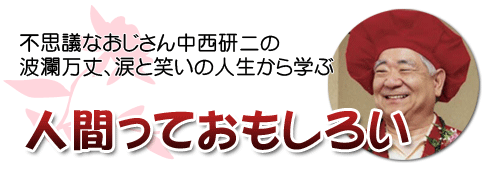
不思議なおじさん中西研二の波乱万丈、涙と笑いの人生から学ぶ
「人間っておもしろい」
第3回 社会と闘う日々、挫折、そしてもう一度生きる決意!
ゲバ棒からペンへ…青年研二の青春と苦悩

立派な大学生になりました!
ある日大学生になった研二が大学に行くと、構内に立ち並ぶ「○○粉砕!」「○○反対!」などと書かれた巨大なたて看板の数の多さに驚いた。「いったいこれは何なのだろう…」と思いつつ歩いていると、本部校舎の前に掲げられていた看板に目が留まった。「教育三法解約ハンガーストライキ決行中!」そこにはたくさんのテントが張られていた。「ハンガーストライキ?」どういうことだろうと思いそこにいた上級生に聞いてみた。
「ハンガーストライキということは、みんな本当にご飯を食べないんですか?」すると「当たり前だ。こうして抗議をしているんだからな」と言う。「そんなことをしたら死んじゃうでしょ?」「バカヤロウ! 俺たちは命がけなんだ!」その言葉にびっくりした研二は、やにわに赤十字の腕章を取り出すと、腕にそれをはめて学生課に乗り込んだ。「ちょ、ちょっと! 本部校舎の前で命がけのストライキをやっている人たちが…彼らの命を救うためにもちゃんと話を聞いてあげてくださいよ!」
すると「あなた、何年生?」「一年生です」「あぁ、一年生じゃぁ分からないだろうけどね、あの人たちはああしていても夜中にご飯を食べてるの。だから大丈夫!」と事務の女性が平気な顔で言った。
「え~? 本当なんだろうか」そう言われたら確かめたくなる性格、その日から自分も一緒に泊り込んだ。時々学生たちの脈などを測りながら、様子をうかがっていたが、一向に食事を取る気配はなく彼らは本当にハンガーストライキを決行していたのだった。その真摯な態度に、研二は感動した。そしてほとんど同世代の若者なのに、国際情勢に精通し命を懸けて世の中を良くしようとしている姿に強い衝撃を受けたのだった。「自分がやっている赤十字奉仕団程度のことでは、平和な世界はやってこない」。

赤十字奉仕団のリーダーだった頃
そのころ研二は総理府が主催する『青年の船』に乗り東南アジアを回るメンバーの候補に挙がっていたが、そんなことより何より、自分の中にふつふつとわいてくる正義感に燃え、全国的に勢いを増していた学生運動へとどんどんのめり込んでいったのだった。
それからは想像を絶する大変な日々。はじめてデモに出たとき機動隊の「つっこめ!」という声にみんな逃げていくのだが、なにせ研二にははじめての体験、素直につっこんだため、当然機動隊に捕まってしまった。片腕を私服、もう一方の腕は機動隊がつかんでおり、なんと双方が自分の手柄にすべく言い争いをしている。だが護送車の前に連行されていったとき、機動隊の隊長が研二の顔を見るなり、「こいつは雑魚だ。放してやれ」と言ったので、ラッキーなことに逮捕は免れたのだった。
そんなことがあってからは、捕まらないように注意深く行動することを覚えた。闘争があるたびに逃げまくったが、相手もしつこく追ってきた。袋小路のようなところに逃げ込んで、時にはもうだめかと思うこともあったが、時代劇の捕り物帖のごとく、さっと裏木戸が開いて土地の人がかくまってくれた。そしておにぎりなどを食べさせてくれた時の人の情けは、今もありがたく研二の心に残っている。
やがて全国の大学の8割に及ぶ165校以上で展開された学生運動も下火となり、命を懸けた運動家たちの願いもむなしく、70年安保条約は自動継続された。そして壮絶な学生運動に身を投じた研二の過酷な日々も収束を迎えたのだった。「なぜ平和を求めて闘わなければならないのか。多くの仲間が投獄され、大怪我をして身障者になり、死者まで出して我々が得たものは何だったのか…」強烈な挫折感と罪悪感で、死にたいほど自分を追い込んでいった。
そのころの研二からは、持ち前の元気も明るさも消えうせ、誰にも会わず半年間自室に閉じこもったままの生活だった。そんなある日評論家のU先生から電話がかかった。忘れもしない新宿ゴールデン街の焼き鳥屋の二階で先生はこう言った。
「世界中があんたの敵にまわったとしても、私はあんたの味方だけど…それじゃ不足ですか?」研二は泣いた。泣くだけ泣いてもう一度生きる決心をした。そして社会に新聞記者として出て行った。
だが新米記者研二は、その世界に恐ろしい罠が待ちかまえていることなど知る由もなかった。
(つづく)
2009年10月15日掲載
